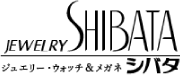神代栗の螺鈿のジュエリーのご紹介です
先日のブログでご紹介したピンブローチ

このピンブローチを作った螺鈿ジュエリーの作家、早川守彦氏の新作のジュエリーを今日はご紹介したいと思います。
神代栗に貝の螺鈿とダイヤモンドがあしらってあります。ペンダントの上部は芥子の真珠です。


『神代栗』
私は不勉強で今回はじめて聞いた名前です。今回、ブログでご紹介するにあたり調べてみました。
神代(ジンダイ)とは長い間、地中に埋もれていた間に濃い色合いに変色した木の呼称です。山崩れや火山の噴火で1000年以上、地中に埋もれていた木を神代木と呼んでいます。
(ちなみに津波や川の氾濫で川底に堆積していた木は埋もれ木と言います)
また1000年以下は半神代とも言ったりしているそうです。
1000年以上、地中で眠っていた木は化石のように変化していきます。その灰色がかった黒褐色の風合いは、人工的に作られたものとは異なります。そんな神代木は河川の改修や土地の造成などで、たまたま掘り出されて発見されます。
「でも植物だから、くさっているでしょう・・・」
そう思われてしまいますが、酸素が絶たれるとかの偶然が重なると朽ちることなく存続していきます。今日、紹介している神代木は栗ですが、調べてみると欅や楠、杉などもあります。発見されてからは、乾燥させたりして家具などに加工されます。ご紹介の神代栗は新潟県の阿賀野川の河川敷から出土しています。
神代の言葉は小倉百人一首の「ちはやふる神代も聞かず龍田川 からくれなゐに水くくるとは」の神代と同じ意味。ずっとずっと昔の神さまの時代からということです。そんな神代木と、これも長い間地球の中で結晶を重ねたダイヤモンドのジュエリー。また螺鈿は正倉院にも納められている日本の伝統技法。

改めて見ると「あ~古代のロマンが秘められてるなぁ」と、少し額田女王のような気分にもなりました(たまたまテレビで岩下志麻さんの額田女王の再放送を見たばかりだったので・・・)
そもそも宝石は地球の中から採掘された鉱物。流木が化石になったジェットなどのジュエリーも以前から使われていますが、宝石には『地球の太古から今への流れ』というものを感じさせる力があるなと思ってしまいます。
早川氏の螺鈿に話を戻します。
向かって右側がタマムシの螺鈿。左側は貝の螺鈿になります。
発色や切り取られたカケラの形。お好みが分かれると思いますが、(あくまでも個人的な好みで)シバタは貝の螺鈿ほうに惹かれます。シバタ店主はタマムシの色合いがキレイと申しておりますが、ジュエリーとして着ける。そうなると鋭角的な角度を作る貝のほうがシャープな印象になるかなと思ったりしております。
「一度、螺鈿のジュエリーを見てみたい」
そう思われましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせ下さいませ。